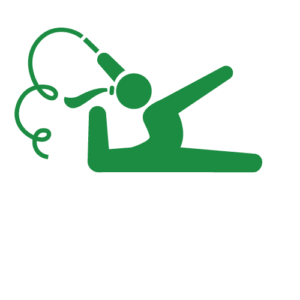公務員のやる気アップは、みんなで考えなければならない問題だ
公務員革命ー彼らのやる気が地域社会を変えるー
太田肇 著
この本を読みました。
公務員の法律、現場の空気、職員たち、自治体への住民の(厳しい)目、それぞれの視点を汲みながら、
自治体職員に"本当の"やる気を持ってもらうという(ほとんど実現不可能な)難題に、諦めずに立ち向かっている良い本だと思います。
出版されたのは2011年で、2025年からは15年も昔の話になります。
民間企業であればちょっと古臭い話になって、今はもう別のトレンドに進んでいぜ!となると思います。
ですが、役場ってところは硬直的な組織と文化を持っているので、現代であっても全く当てはまります。
2025年の本と違うのは、ハラスメントに関する記載が少ないくらいです。
2011年から提唱されている問題が、その後結局どうなったか、という答え合わせができてむしろよいです。
今回は、この本を読んで、私が役場に対して思っていることを少し書こうと思います。
思っていること、と言うのは、
「今の役場に、評価制度、成果主義、細かい管理(マネジメント)を導入したとして、果たして今より良くなるのだろうか?」
という問題提起です。
成果を決めて評価することは難しい
役場職員の成果は何なのか
役場職員の成果はどのように計るか
大きくこの2点が、評価制度や成果主義を実装するのに難しい理由です。
難しいものを無理やり実装すると、評価は形がい化し、努力しているとか頑張っているとか何時間残業しているとかで評価が決まってしまう。
ということを、この本は、ちゃんと論理的に順序だって説明してくれます。
そもそも、役場の仕事というのは成果が大きいものが評価が良くて、成果が小さいものの評価を低くして良いのか、という点からすでに疑問です。
自治体はセーフティーネットの役割もあるので、単純な数字の大小によって成果の大小を決めてはならないと思うのです。
例えば、住民100人に影響する施策は、住民1人に影響する施策の100倍成果が高く評価される、とは単純にはならないはずです。
たとえ1人の住民のための制度であっても、時間を割いて働いて欲しいと思っています。
難しい仕事をやる気頼みで提供してもらっている
さて、タイトルについての話に進みます。
役場職員を雇用する地方自治体というところは、人口減少に伴い今後お金が先細りしていきます。
高額な報酬でアドバンテージを作ること、自治体の中で役職を上げることですら、モチベーションにならない事を示しています。
更に、いつからか住民やマスコミから公務員をバッシングする(公務員は反撃してこないから)のが普通になりました。
(バッシングは最近かもしれないが)1990年くらいまでは給与がそれほど高くなくても良かったようです。
田舎では他の企業と比べて給与が相対的に良かった(都会と田舎の民間企業の給与差よりも、役場職員の給与差の方が小さい)のと、役場職員の仕事は単純な定型的な作業だったからです。
要は、仕事が楽だから給与が低くても大丈夫だった、というわけです。
そこに2011年からITとデジタル化の波が押し寄せてきます。
この本の素晴らしい所は、2011年時点ですでに、デジタルやITによって単純な定型作業は消えてなくなると言い切っているところです。
2025年の現在で、単純な定型作業は消えてなくなっていないところが残念ではありますが、その流れは少しずつですが確実に進んでいます。
時間が進んで単純作業がなくなると、役場職員は何をする事になるのか。
それがまさに、「やる気」がないと務まらないような、複雑で面倒くさい仕事になります。
「まちの将来について計画・提案し、問題解決しながら地域を経営する」
これが複雑で面倒くさい仕事で、自治体業務の中心的役割となります。
役場では決められた事務を粛々とこなすのではなく、自ら政策を立案し、企画を立てて業務を行わなければなりません。
これを実施するのは受け身な態度ではもはや通用せず、自ら考え行動する自発的なモチベーション=やる気が必要不可欠になります。
では、具体的に役場の仕事はどのようなものがあるか考えてみましょう。
ITとデジタル化、アウトソーシングで申請を受け付けてハンコを押すといった単純作業は無くなります。
(お金が先細る中で)残る作業は、災害・防災といった安全、健康・福祉・子育てといったその地で生活するのに直接影響するものになるでしょう。
困難な状況に陥った時に助けてくれる存在、役場の仕事はだんだんと突発的・日常的に生活に直結する部分に収れんするでしょう。
住民が職員にやる気を出してもらわないと私たちの生活が豊かにならない
ここまでを住民視点でまとめると、
「住民の生活に密着する仕事(サービス)を、職員のやる気を頼りに提供してもらっている状態」
に遅かれ早かれなっていくわけです。
これで、タイトルの「役場職員のやる気アップは、みんなで考えなければならない問題だ。」に繋がります。
役場職員のためではなく、私たちの生活に影響する問題として、職員にはやる気を出してもらうように、住民は動かなければなりません。
「いや、役場職員は自発的にやる気出せよ!」
と思われるかもしれません。
好きでその仕事に就いたんだから当然のことだとも、思えるっちゃ思えます。
繰り返しになりますが、これまではやる気がなくても行えた単純作業でした。役場職員は頑張って仕事をしない、というのが世界的に見ても共通認識だったように思います。(ズートピアのナマケモノ フラッシュを後述)
その時代から、仕事の内容が変化してきているのです。
そして、やる気がない(見せかけのやる気)が問題になるのは、実は普段の業務では見えづらいものです。
やる気が問題になるのは、困難な状況に陥っている時(簡単に言うとイレギュラーが発生している時)です。
「申請書の記入漏れがあった時にどのように対処するか」(通常は申請却下にする所、気を利かせて電話で内容をヒアリング←これをしなくなる)
「火事の現場で火の中に飛び込むかどうか決める一瞬」
そんな状況でやる気が問題になります。
やる気を出さなくてもバレないタイミングで、本当のやる気か、見せかけのやる気かが問われます。
役場職員は人間なのです。
ズートピアというディズニー映画でナマケモノの役場職員が出てきます。名前はフラッシュ(閃光)。
彼が住民検索で名前をタイピングするんですが、そのスピードがものっそい遅くて主人公たちはとってもイライラしちゃうって描写です。
世界的に役場職員のイメージってこんな感じなんだと思います。
これこそまさに、給与が低くても単純作業だから大丈夫な状態です。
大丈夫ってのは、給与への貢献度合いを自分で設定できて、更に自分で仕事量を調節することができる状態をいいます。
役場職員は人間なのです。
ということで、私たち住民は勢力を上げて、役場職員のやる気アップさせる打算的行動をする必要があります。